参考改装後
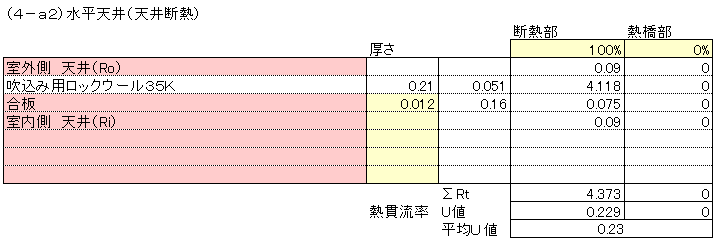
住宅・建築物省エネ改修等推進事業対象事業の要件
補助率:1/3(上記の改修を行う建築主等に対して、国が費用の1/3を支援)
住宅の場合は上限50万円/戸
※バリアフリー改修工事又は耐震改修工事を行う場合にあっては、バリアフリー改修工事又は耐震改修工事を行う費用として、
25万円を加算。(ただし、バリアフリー改修工事又は耐震改修工事部分は省エネ改修の額以下)
平成25年5月29日(水)~平成25年6月26日(水) 消印有効
応募にあたっては、下記の①~⑤の要件を全て満足する必要があります。
① 躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。
② 建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して概ね10%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施するものであること(※1、※2、※3、※4)。
③ エネルギー使用量の実態を把握する計測を行い、継続的なエネルギー管理、省エネルギー活動に取り組むものであること(※5)。
④ 省エネルギー改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事に係る事業費の合計が500万円以上であること。(※6)(ただし、複数の住戸における事業をまとめて提案し、上記事業費以上となる場合も可とする)
⑤ 平成25年度中に着手するものであること(※7)。
| ※1 | 戸建住宅及び共同住宅の住戸部分に限り、別表1-(1),1-(2)に掲げる改修タイプの早見表を満足する改修内容で応募する場合には、戸建住宅全体及び共同住宅の住戸部分に限り概ね10%以上の省エネとなるものとみなします。なお、共同住宅の共用部分を含む省エネ改修を行なう場合は、住戸部分と共用部分を含めた共同住宅全体で概ね10%以上の省エネ効果が見込まれる必要があります。 |
| ※2 | 改修工事を伴わず、エネルギー使用量等の計測のみを行う事業は対象外です。 |
| ※3 | 概ね10%以上の省エネ効果の評価においては、エネルギー管理等によって設備の運用を改善すること等の効果は含みません。 |
| ※4 | 太陽光発電設備は、補助の対象となりません。また、導入に伴う発電量を省エネ効果に加えることはできません。 |
| ※5 | 住宅におけるエネルギー使用量の計測は、住宅全体のエネルギー使用量を毎月把握(計測)するものとします(エネルギー事業者等からの請求書等に基づき把握(計測)するものも可とします)。なお、計測等に係る費用は補助の対象となりません(ただし、P.4 の<補助対象となるものの具体例>に掲げるHEMSは補助対象とする)。 |
| ※6 | 本事業の補助対象となり得る改修工事(省エネルギー改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事)以外の工事については、事業費に含まれません。 |
| ※7 | 省エネルギー改修工事(計測機器の設置も含む)、バリアフリー改修工事、耐震改修工事のいずれかの工事への着工をもって着手とみなします。 |
断熱改修は健康にいい
近畿大学 岩前篤教授 コラムで発表されています。
アトピー、ぜんそく等を和らげる効果をデータ―で説明されています。
6回シリーズです是非参考にしてください。
| 年間消費エネルギー計算は購入した電気、ガス、灯油等を調べて計算します。・・・・・・・・・計算参考にしてください |
| 10%削減の根拠説明ストーリー | |||
| ①直近1年の購入エネルギーを調べる ②一次エネルギーに換算する ③一次エネルギーを用途別に分配する ③省エネリフォームをする部位を決める |
|||
| 暖房 | 外皮の省エネ量を計算 | 換気のエネルギー回収を計算 | 高効率機器の省エネを計算 |
| 冷房 | 同上 | 無し | 同上 |
| 給湯 | 高効率設備機器の省エネを計算(エコキュートの場合はAPFで計算) | ||
| 照明 | 同上(エネルギー消費効率lm/w) | ||
| その他 | ゼロエネルギー住宅にする場合は創エネ、蓄エネで相殺する | ||
外皮の計算は熱貫流率計算すると削減率が計算できます。
参考改装後
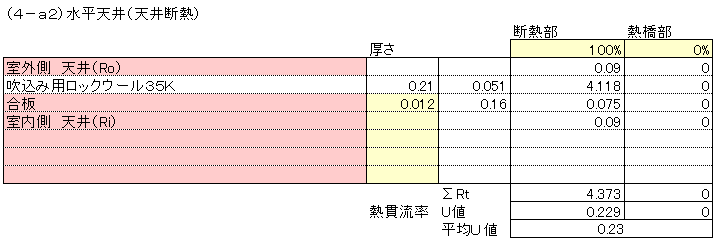
次世代省エネ基準に合格する熱貫流率です。
削減率=(1-改装後のU値÷改造前のU値)となる
削減量=改装後の用途別一次エネルギー(MJ)÷改装前用途別一次エネルギー)
削減率=削減量(MJ)÷一次消費エネルギー総量(MJ)