投資型減税
1年
控除率10% 控除対象限度額200万円
工事を行なった年分
1.耐震工事を行なった者が自ら居住する住宅であること
2.一定の区域内における改修工事であること※3.昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
4.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修をおこなうこと
5.住宅耐震改修証明書(地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定認定検査機関または登録住宅性能評価期間が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告を行なうこと
※2.標準的な工事費用相当額
改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、
当該改修工事を行なった面積を乗じて計算した金額
木造住宅の 耐震リフォーム 事例集(静岡県)

※3.適用区域について
地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域に加え
平成21年1月1日より地方公共団体が耐震診断のみを補助している地域が新たに含まれます。
補助金の下限要件も撤廃されます。
横浜市の補助金交付手続きhttp://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/bousai/mokutai/mokukaishu/zeikin.html
横浜市の補助金交付手続きの流れ
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/bousai/mokutai/mokukaishu/mokukin-huro.pdf
住宅耐震改修照明申請書
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/bousai/mokutai/mokukaishu/shotoku_zei.pdf
建築物の耐震診断結果報告書
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/bousai/mokutai/mokukaishu/yoshiki.pdf
証明書発行窓口
調整局建築企画課
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/gene/iten/iten.html
登録住宅性能評価機関
http://www.hyouka.gr.jp/kikan/hyouka_search.html
指定確認検査機関
http://www.icba.or.jp/j/ken/siteikikan.htm
地震保険割引のための証明書はこれらの証明書で代用が出来ますので、必要な場合はご自身で写しをとってご利用ください。また、これらの証明書の発行対象でない場合、改修設計を行った建築士で証明書の発行が可能か問合わせください。
住宅
ローン減税
平成21年1月1日~平成25年12月31日に住居を開始した方で、住宅ローン減税の最大控除額※7まで所得減税が控除されない方については、所得税から控除しきれない額について、個人住民税から控除されるようになります。ただし、個人住民税からの控除額は、当該年分の所得税の課税所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)が上限となります。
※7.毎年末のローン残高の1%
増改築等工事に係る適用要件(抜粋)
工事費100万円超及び増改築工事の床面積が50㎡以上となる誇示(耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び一定の省エネ改修工事を含む)
住宅ローン減税 平成21年(PDF)
http://www.mlit.go.jp/common/000029447.pdf#search='住宅ローン減税 平成21年'
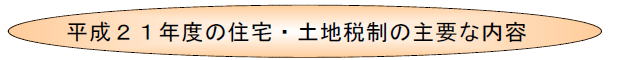
H18~21 3年間 1/2を減額
H22~24 2年間 1/2を減額
H25~27 1年間 1/2を減額
当家屋に係る120㎡分まで
2.耐震改修費用が30万円以上であること
3.耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告すること