| 家庭菜園 プランターで見つけた虫た【害虫】 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本的には無農薬の家庭菜園を目指していますが予防対策がわからない初期は下記の農薬を使って駆除その後は無農薬対策を実施、事例コガネムシの幼虫はダイアジノン粒剤又は、オルトラン粒剤を使用したがコガネムシの産卵は土に潜り産み付けることが判明し、その後は不織布で土の表面をカバーして産卵出来ないようにすることで完全に回避できるようになった。 ナメクジは夜な夜な巡回をして捕殺が効果的、カブラガヤの幼虫は昼間土に潜り夜活動するので夜間に捕殺と土に潜れないように不織布を土の際の茎に巻きつけて防止する・・・・数の少ないプランターの栽培だからできることです。「夜間巡回」が日課になりました。 |
|||||||||||
INdex アオムシ アゲハチョウ アザミウマ イチゴハナゾウムシ ウリハムシ ウリンウワバ おんぶバッタ カブラヤガ カマキリ カメムシ コウガイビル コガネムシ コガネムシのサナギ コナガ コバネイナゴ コマダラコガネ セミ ソラマメヒゲナガアブラムシ だんご虫 ツマグロヒョウモン テントウノミハムシ トカゲ 殿様バッタ ナノクロムシ ナメクジ ハダニ 葉もぐりバエ フキメイガ フタトガリコヤガ ブドウスズメ ブドウスカシクロバ マイマイガ ミツモンキンウワバ ムカデ モンシロチョウ ヤモリ ユウマダラエダシャク ヨモギエダシャク 人参いた虫 ねずみ |
詳しくはネット検索してください。 虫名で検索するといっぱい出ています。 |
||||||||||
| 2010年もきゅうりのプランターに産み付けられていました。 2009年4月24日コガネムシ 早くも犠牲者 百成ひょうたんが遭えなく溶けていきました 原因 寒さかな? しかし、土を掘るとコガネムシの幼虫を発見パーライトは効果がありませんでした。 9月23日コガネムシ成虫を捕獲5月23日コガネムシの犠牲者、金のなる木もぐったり 恐るべしコガネムシの越冬隊 |
ゴーヤのプランター金のなる木杉の木クリスマスローズ、きゅうり、ナス、ひょうたん、へちま、しし唐、度のプランタンにも卵をう産みつけていくコガネムシとの戦い3年越し |
 |
|||||||||
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |
|||||||||
| 天敵線虫スタイナーネマ・グラセライやスタイナーネマ・クシダイは、土壌中でコガネムシ類の幼虫の口から体内に入り、線虫と共生している細菌によって幼虫を殺すそうである。このような生物農薬も商品化されている。アセビニコチン液やアセビ団子も効果がある http://www.kirakira.ne.jp/~kenzotabuchi/link25.htm・・・・HPから転記しました(まだ挑戦していません2010年10月18日) |
|||||||||||
| コガネムシのサナギを発見 2009年6月12日 コガネムシの正体 幼虫 サナギ 成虫 |
.jpg) |
.jpg) |
|||||||||
| ダイアジノン粒材の効果がありました、散布した当日あめが降り 虫の息の幼虫を土の上で発見 | |||||||||||
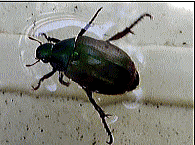 |
|||||||||||
| 2017年6月22日昨夜の雨水のたまったトレーに浮かんでいたナガチャコガネ捕殺 | |||||||||||
| 虫発見の野菜 ニガウリ(ゴーヤ) スナップエンドウ カラーピーマン べチニア ジャガイモ きぬさや ライムレモン チューリップ ナス ジャガイモ イチゴ 水菜 大根 ニガウリ トマト ゴールドクレスト ひょうたん オクラ 空豆 キュウリ |
|
 初確認→ 初確認→ |
|||||||||
| 我が家の周辺で発見したコガネムシ |  |
 |
|||||||||
| コガネムシの幼虫には抜群の効果オルトラン粒剤 | 20120703撮影 コマダラコガネ |
20160611撮影 シロテンハナムグリ |
|||||||||
| オルトラン粒剤 家庭菜園・草花・背の低い庭木鉢物などの根元や葉に散布する他に、植え穴にまくなどの利用法があります。 住友化学嚥下尾のホームページより |
 |
効果 |
 わが家のコガネムシ対策 |
||||||||
| コガネムシ対策「完璧に防御」 発生時期一年中(幼虫)、5~8月(成虫)雌成虫は交尾後、土中に産卵、産卵時期には、畑や芝地などに卵を数十個ずつ数日間にわたって産みますが、鉢やプランターの中にも産卵。成虫にはスミチオン乳剤やオルトラン水和剤を散布。コガネムシ成虫の姿を見かけたら、付近に卵を産み付けた可能性が大きいので、ダイアジノン粒剤3を植物のまわりの土に混る。毎年発生している場合には春先に苗を植え付ける時に始めから土に混ぜておく。住友化学園芸より わが家の対策 成虫は花や葉を食べる困りものですが羽根があり対策は困難、しかしその幼虫はさらに大きな被害をこうむります。土に潜り卵を産み付けその後幼虫になると旺盛な食欲で根を根こそぎ食べて野菜たちを枯らしてしまいます。その対策に卵を産ませない、すなわち潜らせないようにプランターを不織布で覆うことにしました。その後は完ぺきに防御 |
|||||||||||
| コガネムシの戦いに勝利宣言・・・・勝因は卵を産ませないこと→実践:不織布で地表を覆い成虫を潜らせない | |||||||||||
| ニガウリ(ゴーヤ) | 2010年6月13日 苦瓜の葉が虫食いにあっています。それも1枚だけ? |
.jpg) |
.jpg) 苦瓜の茎にいた、アブラムシ? |
.jpg) テントウ虫も忙しそうにしています。 |
|||||||
| スナップエンドウ | 2011年5月6日 スナップえんどうにやってきたアブラムシ、動きが鈍くすぐ捕まえることが出来ますがとにかく数がすごい |
ソラマメヒゲナガアブラムシ アメアブラムシ等 |
|||||||||
| カブラヤガの生態 葉っぱに卵を産み付けて大きく成長すると昼間は土に潜り、夜な夜な活動する。大食いの害虫です。 |
|||||||||||
| カラーピーマン | 5月31日 カブラヤガの幼虫に食べられたカラーピマン カラーピーマンの葉っぱが無残にも朝起きると食い荒らされていました。 どこにも虫はいません。 NETで確認したのを思い出して土を掘り起こして調べたところ一匹いました。 いつもの排水溝へ始末 この虫が生息すると葉や花が大きな被害にあいます。 葉が食べられていたりするとまず葉の裏を確認、いなければ土の中を疑ってください。 本当に大食いの虫です。 |
.jpg) |
.jpg) |
写真は天日干しをしている根切虫のいた土 |
|||||||
| カブラガヤの成虫と思われます 4月25日ジャガイモの土の上で発見 |
|||||||||||
| べチニア | 根切り虫 ぺチニアのプランタンに潜んでいました 花と葉っぱが見事に食べられているのを6月12日発見 6月13日土を掘り返して発見 |
 |
.jpg) |
.jpg) |
|||||||
| 2011年4月2日そら豆に居た根切り虫捕殺早速ダイアジノン粒状3を散布 | 葉の丸まっている裏に隠れてるつもりかな? | ||||||||||
2017年3月30日サナギ発見 ミモザの植木鉢 大阪府のヨトウムシのサナギにそっくり根切り虫のようです |
カブラガヤの幼虫捕獲の秘訣、焼き鳥の串で根っこのそばを1㎝位ほじくると簡単に見つけることが出来ました2011年6月14日捕殺4匹、ジャガイモの根っこで発見。 | ||||||||||
| ジャガイモ | 被害にあったジャガイモの葉、葉も食べられていますが、茎もかじり葉の根元から枯れ落ちます。ふ化直後の葉裏に群棲している時に防除するのがポイントです。浸透移行性剤のオルトラン粒剤やオルトラン水和剤は効果が続きます。ある程度大きくなった幼虫は土中に隠れ、夜間活動するので誘殺剤のデナポン5%ベイトを株元にまいておくと効果的です。収穫間際の野菜にはゼンターリ顆粒水和剤が使用できます。 | カブラガヤの糞です。 | |||||||||
| 2011年6月14日 ジャガイモが被害いに会いました |
 |
||||||||||
 大阪府のHPより 大阪府のHPより |
 |
↑ 2015年5月19日 ジャガイモの葉を食べていた ←カブラガヤの成虫 |
|||||||||
 |
2018年5月26日ジャガイモの葉裏で捕獲 | ||||||||||
| 生態 ・年2~3回発生し、幼虫態で越冬する ・本畑初期にタバコを地際部から切断し大害を与える ・特に蔬菜類の跡地付近の畑に被害が大きい ・成虫は夜間活動性で、下葉や根際に1~数粒ずつ産卵する。(1雌当り平均500粒前後) ・ふ化幼虫は最初葉裏で生活し、葉に小円孔状の食痕を残すが、3~4令以後は日中は土中に潜み夜間のみ摂食する ・早朝に被害株の根元を軽く掘ると灰褐色あるいは薄ずみ色の幼虫を発見できる ・老熟幼虫は土中で土室を作り、内部で赤褐色の蛹となる ・越冬幼虫は翌春再び接触活動をはじめる |
|||||||||||
| 勝利宣言防除対策 ・冬期ふるいに掛け幼虫を捕殺する ・捕殺…夜間活動するので巡視して葉裏などに潜んでいる幼虫を捕殺する、食欲旺盛なので被害のある葉を重点操作 |
|||||||||||
| きぬさや | 2010年12月21日 葉もぐリバエきぬさやに大量発生 毎日圧刹、プチプチをつぶすような感じで小さな音もします。 一番多い葉もぐりバエのきぬさやの葉っぱです。8匹圧刹しました。圧殺では退治できないことが判明、やはり寄生された葉を取り除くのが一番いいようです。 |
 |
新しい葉にはいません成長したかたい葉っぱにもぐりこんでいます。同じ葉に何匹ももぐりこんでいるのが意外です。 上の写真はサナギとお絵かきをした痕跡です。さなぎの段階下ははっきり居場所が確認出来圧殺出来ますが幼虫はなかなか見つけられません。お絵かきの葉っぱは摘み取るのが一番でした。すごい繁殖力です。 |
 |
|||||||
| スナックえんどうにもすごい数の葉もぐりバエが寄生 | 2011年5月6日 黄色い粘着テープは優れモノですいっぱいの子バエが付きました。それでも葉の中にはスゴイ数のハモグリバエです。 |
||||||||||
 |
 |
||||||||||
| レンゲの葉にもマモグリバエ発見摘み取りました。 | 2016年10月19日 2016年6月29日撮影モンシロチョウ | ||||||||||
| 卵とサナギと成虫です。 ハモグリバエのサナギを捕獲してクリアーファイルに入れて20日ほど経つと小バエに羽化しました。 |
|||||||||||
| アゲハチョウ |  |
←成虫 ↓幼虫の後期 |
↓幼虫の初期 | ↓卵 | |||||||
| ライムレモン | ライムレモンの木で発見したアゲハ蝶の幼虫、写真を撮っている時も卵を産みつけていきました | ||||||||||
| アゲハチョウ |  |
2010年10月6日発見「キアゲハの幼虫」 細々とでも発生を続けてくれることを願っています。家庭菜園でこの幼虫を見つけられたらすぐにやっつけたくなる気持ちは分かりますが、一度は飼ってみられてはどうでしょうか。羽化したときにはきっと感動すると思うのですが。。。。 HPで見つけたコメント・・・・遅かったです全て捕殺しました |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 2020年4月9日イチゴの葉に止まっていたアゲハチョウ | |||||||||||
| 2012年6月16日訪問者↑ | 2012年13日卵発見 数日前にキアゲハがやってきて卵を産み落としていました直径約0.7ミリくらいの小さな玉G歩を2個発見しました。親指の左上に産み付けていますがカメラのピントボケで見分けがつきません。 |
 |
|||||||||
| 2016年10月19日殿様バッタ |  |
||||||||||
| チューリップ | チューリップのハダニ | 肥料やけかと思っていました、新芽のときから少し変でした、本で調べるとサビダ二塁と判明(肉眼では見えないほど小さな害虫)葉は巻くように変形、委縮 | |||||||||
 |
 |
2000倍にコロマイト乳剤を希釈してダイン(展着剤)を混ぜチューリップに散布、よく効きました。 | |||||||||
| ナス |
アオムシ(青虫)は、チョウ目(鱗翅目、チョウやガ)の幼虫のうち、長い毛で体を覆われておらず、緑色のもの。緑色でないものを含めイモムシ(芋虫)といい、長い毛で体を覆われているものをケムシ(毛虫)という。これらは大まかな区分であり、明確な定義があるわけではない。 9月20日なすで見つけたフキメイガヘタに5㎜位頭を突っ込んでまさにナスのの中へ入り込もうとしていたところを見つけました。即捕刹人参にもきぬさやの葉を食い荒らすミツモンキンウワバの幼虫と白い小さなのが卵です。卵は葉に1個づつ産みつけられ、約4日間でふ化する。農薬を散布するのが最も一般的な防除法です。テフルベンズロン(ノーモルト)乳剤、クロルフルアズロン(アタブロン)乳剤、などのIGR(昆虫成長制御)剤の効果が高いです。とのこと |
9月24日大根の新芽 アオムシ 小さな双葉からやっと本葉が成長してきたところを腹いっぱい食べられました。捕殺しました。 |
|||||||||
| 人参の葉にいた虫達 「ミツモンキンウワバ」 「キアゲハ」 |
|||||||||||
| 水菜 |  |
←2015年10月17日水菜にいた青虫 | |||||||||
| 大根 2015年10月17日大根の葉を食べて成長したサナギ→ |
 |
11月7日 大根もきぬさやも被害にあっています。毎日幼虫と卵を発見しては捕殺していますがきぬさやの豆を食べた虫は確認できていません 右の写真はミツモキンウワバがサナギになる前の糸で巣をつくたところを発見マリーゴールドにいた |
|||||||||
| ニガウリ | .jpg) |
20010年6月17日 苦瓜の葉っぱを食べたのはナメクジそれともだんご虫 2012年6月14日カブラガヤの幼虫を発見しました。 |
ナメクジ |
だんご虫 |
|||||||
| ナメクジの被害 ナメクジをナメたらあきません。大根の葉っぱが被害を受けました。ヤトウ虫と同じ被害です。捕殺は雨の降る夜が効果的。 |
ナメクジの卵発見 半透明な殻付きの玉 直径が2-3mm 殻につつまれていました |
||||||||||
| ナメクジの生態 昼間は日陰の暗いところに潜み夜間活動 卵を地表に産み落とす(カタツムリのガラと同じ半透明でまん丸い卵) 植物体の柔らかい部分、花弁、新芽や若い葉を好んで食害します。食害された部分は穴が開くため、せっかく咲いた花がだいなしになり、イチゴは地際に実るため、穴を掘ったように食べられます。また、新芽部分が軽く食害された場合、葉が生育するとともに葉に穴が開いてくることがあります。 |
|||||||||||
| 勝利宣言 プランターだから出来た事 夜な夜な巡回してナメクジを捕殺する 昼間隠れそうな特にプランターの水抜き穴を鉢底ネットでふさぐ 昼間地表を点検 卵を見つけて処分 |
|||||||||||
| トマト | 2011年7月22日 トマトの葉を食べているところを発見 シャクガの仲間 |
 |
|||||||||
.jpg) |
.jpg) |
↑20120622発見 ヨモギエダシャク(幼虫)と推測 |
|||||||||
| トマトの茎の中にもいました。2011年8月5日 |  |
ニホントカゲ? | |||||||||
| ムカデ アースのHPリンク |
 |
 |
 |
 |
|||||||
| ムカデに噛まれたら 絶対にしてはいけない事
|
驚きです 2010年6月16日ムカデを知らない家内は大きなげじげじを漂白剤で退治したのでかたずけてほしいとメモがありました。知らぬは、強い! ゲジゲジもどきもたじたじ |
2015年7月23日ムカデ捕殺 素手で鉢植を移動したら飛び出してきた。今後も気を付けて移動するように考える。数年前に洗面台にも現れた。 |
2017年6月26日土を乾かすためのビニールシートを広げた時に飛び出してきたムカデ 刺されなくてよかったサンダルで圧殺 | メダカを狙う蜂? アカガネコンボウハバチ? |
|||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 2018年9月16日発見セスジスズメ | 2021年4月29日イチゴの葉裏で見つけた ヨトウムシの幼虫と思われる |
2021年5月19日車のボディーに止まっていた トビゲラと思われる | |||||||||
| しゃくとり虫 |
|||||||||||
| ゴールドクレスト | 5月31日ヨモギエダシャク(幼虫)かな? ゴールドクレストにも虫を発見 尺取り虫のような姿です。 |
.jpg) |
.jpg) |
||||||||
| 青虫:ウリキンウワバのようです。 刺さりませんし毒もありません 対処法補殺 どうも調べていると上の尺取り虫の成長したもののようです。長さは3センチくらいになっていました。 本日補殺6匹 どうも殺菌剤は効果が疑問 補殺あるのみ 黒い糞が葉っぱに散乱しているので見つけやすいと思いますが、グロテスク 噛まれる刺される晴れるはありませんでした。ひょうたんにも尺取り虫がいました 体長7ミリくらいの小さな幼虫が葉っぱをむしばんでいます。 |
.jpg) |
||||||||||
.jpg) .jpg) 移動して新しい葉にありつこうとしています |
.jpg) |
.jpg) 擬態のうまさ |
|||||||||
| ひょうたん | 2011年8月9日ヒョウタンの葉から捕獲 | 大量発生20匹ほど圧殺 | |||||||||
| 20110907 サナギを発見、右端は白いのが卵と思われます。 | |||||||||||
| ヒョウタンの葉にもアブラムシ発生2011年8月9日 | べにかXは効きました。 | ||||||||||
| 2010年6月14日 ひょうたんの害虫が葉を食べています。尺取り虫の小型体長12ミリに成長 対策 STダニエール1000(殺菌剤) ダイン(展着剤)を混ぜて |
.jpg) 薄めて葉に散布 |
 |
|||||||||
| オクラ |  |
オクラの害虫 フタトガリコヤガ 背中には柔らかいとげがあり、触れるとかぶれることがあります。 |
 |
おんぶバッタ | |||||||
| キュウリにいました。7月26日撮影ウリハムシが7匹飛んでくる虫です。小さくきゅうりの葉をつまみ食いしています。 | |||||||||||
| 空豆 | ルリクビボソハムシかな?そら豆の葉裏に居たところを撮影 |
||||||||||
 |
 |
||||||||||
| 2017年3月5日は啓蟄です。 3月12日カメムシ発見 |
2009年8月1日 ヒイラギにいたところう捕獲、羽がない?標準的なカメムシと判明 クサギカメムシ |
2010年10月17日 カメムシはゴーヤの実に止まり果汁を吸っているのを良く見かけます。 |
2017年4月14日 イチゴの葉にカメムシ |
2021年4月7日 クサギカメムシ家の前で発見したのと同じカメムシが欅の木に密集していた |
|||||||
| イチゴ |  |
 |
 |
クサギカメムシの卵 | |||||||
 イチゴの葉をむしばむ害虫 |
 |
 |
 |
||||||||
 |
イチゴハナゾウムシのイチゴの葉に来たイチゴハナゾウムシ。体長3mmくらいの小さな小さなゾウムシです。バラ科の植物の害虫で、蕾に卵を産みます。木いちごなどに花が咲くこの時期に多いそうです「5㎜の大物を捕殺2018-4-15」 | 2016年11月28日イチゴの葉を食べた虫捕殺 | |||||||||
.jpg) |
 |
←2017年7月5日イチゴの葉を食べた犯人 サカハチチョウの幼虫か? 2017年10月27日2匹補足→ |
 |
||||||||
| イチゴについた虫発見コナガによく似ています。 少し大きくなったイチゴの青虫→ ブロッコリーにもいました。弦ありインゲンにも! ベニフキノメイガ シロイチモジヨトウではないかとHPで見つけた イチゴの被害 葉を食べられる |
 |
コバネイナゴ(食用)2009年8月2日 辞書調べ 体の側面に濃茶色の筋がはいった明るい緑色のバッタ。翅は短く、腹端を越えない場合が多いが、個体差があり、長翅型のものもけっこう見られる。 水田やその周辺の草原などに極めて普通。イネの害虫だが、イネ以外の雑草も良く食べる。 佃煮として食用にもなる。 |
|||||||||
| キュウリ | |||||||||||
| きゅうりにいたカメ虫 | .jpg) |
.jpg) |
|||||||||
| ツマグロヒョウモン→ 4月10日捕獲 三色すみれの葉を食べて 成長するそうです.ケヤキの枯れ葉にしがみついていました,なぜプランタンから離れたのかは不明? |
 |
.jpg) |
|||||||||
| 2010年7月10日撮影 ツマグロモンチョウメス |
2016年11月6日撮影 ツマグロヒョウモンの成虫オス |
ツマグロヒョウモンの成虫メス 2010年7月10日撮影 |
|
||||||||
 |
この小さな虫がヒイラギの新芽を食べていました テントウノミハムシと判明 成虫も葉に止まっていました。 |
 |
.jpg) |
 |
|||||||
 |
2016年8月20日 ツマグロヒョウモンの幼虫 |
 |
|||||||||
| セミ |  |
 |
 |
||||||||
| 2016年7月29日 アブラゼミ |
2016年8月2日 ミンミンゼミ |
2016年8月2日 ニイニイゼミ |
|||||||||
| 20108月年8月27日 かまきり虫発見 |
 |
 |
 |
||||||||
| 2016年6月29日 小さなカマキリ |
カマキリ 2016年10月15日 |
||||||||||
| マイマイガ |  |
 |
|||||||||
| 2017年5月9日マイマイガの幼虫 駐車場から道路を横断中に発見 | ガガンボ「人畜無害」 駐車場で発見 |
||||||||||
| バッタ | ヤスデ | クロイロコウガヒル | ブドウスズメ | ||||||||
バッタ 2011年7月22日弦ありインゲンの葉等を食べていました。 |
日当たりの悪い、湿った腐植物の多い土壌が発生源 ヤスデの駆除方法 |
.jpg) 大好物がナメクジだそうです。 ナメクジの天敵 11月10日撮影 |
 |
||||||||
| 大根 |  |
ナノクロムシ 大根の葉っぱの上で見つけました ←の写真はブログで見つけました すみません他人の映像です写真にリンクを張りました。 自家製の写真→ |
|||||||||
 |
5月13日ブドウスカシクロバ |  |
空豆に繁殖 突っつくと糸を引いて落ちていきます。たぶんアザミウマの類と思います。 |
||||||||
 |
ユウマダラエダシャク 鳥の糞に擬態していると言われる。 |
 |
カブラハバチの幼虫 2015年12月9日 真っ黒な幼虫が大根の葉を食べていました |
||||||||
| ナス |  |
ナスの葉が委縮して成長が止まりました。 ウスミドリメクラカメムシ、アオクサカメムシのカメムシに生き血を吸われたと思われる。 又はチャノホコリダニ虫の体長は0.2ミリで非常に小さく、肉眼では見えない。 |
|||||||||
 |
2015年5月21日カブラハバチの幼虫かなジャガイモにいた虫 幼虫はナノクロムシともよばれ、イモムシ様の形態をした黒い虫で、体長15~18㎜。セグロカブラハバチはやや色が薄く灰藍色で体側に13個の黒紋がある。成虫と芋虫はリンク先で確認してください、ガラケイのカメラの性能では接写がうまく取れませんでした。 |
 |
|||||||||
 |
 |
 |
鼠の被害が葉牡丹イチゴ大根の苗、サボテン、イチゴで発生 ネズミ取りシートを設置して2日目で捕らえました。2016/2/16 |
||||||||
| 種類はクマネズミと思われる 粘着シートで捕獲 |
クマネズミは運動が得意です。外の電線・排水パイプも簡単に上って、どこからでも入ってきます。寒さに弱いので建物の中に巣をつくることが多く、天井裏で走り回るのはこのクマネズミです。動き回りながらフンをするので、移動ルートのあちこちにフンを残していきます。確かにいたるところで発見、サボテンの周りに2階のエアコン室外機周辺など | 住まいは雨戸の中から鼠の嫌うスプレーを噴射後エコキュートに引越しをしたのではないか | |||||||||
 |
2016年6月8日ヤモリを初実写 我が家の周りにはかなりの数のヤモリがいると思われるこの写真に捕らえたヤモリが今までに一番大きいものだと思う体調12㎝はあったかと! 食性は動物食で、昆虫やクモ、ワラジムシなどの陸生の節足動物を食べていると言うことです。 |
||||||||||
 |
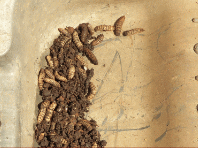 |
 |
 |
||||||||
| 油粕に水が入り放置したため大量のウジ虫が発生土に埋めるが生存していた土の中から1個づつ捕獲して排水口へ廃棄 | 2018年4月9日 紫式部に4匹もいた幼虫 |
2018年9月28日 トカゲを玄関先で発見 |
|||||||||
 |
 |
 |
|||||||||
| 2019年8月21日 ゴーヤをかじっていたとみられる鼠を捕獲 |
茄子の葉裏で発見 テントウムシダマシ幼虫 |
||||||||||
 |
 |
||||||||||
| 2020年8月4日 カラーの葉を蝕む青虫 |
|||||||||||