| 緑のカーテン運動「A2Y家庭菜園」 同じ場所に同じプランターで栽培するコツは畑と違い毎年土を入れ替える(ローテーション)することが基本です。連作障害防止 |
||||
 |
 |
 |
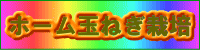 |
 |
 |
もくじ 失敗の連続 土づくり 種まき プランターに定植 ネット張り 水やりと追肥 収穫の始まり 真夏の水対策 強い日差しにめげる 追肥対策 これでもかの追肥 どんどん成長 唖然突然の出来事 撤収 あとがき 収穫 肥料 2012年の実況 2013年の実況 2013年プランター撤収 2008年から の写真日記INDEX |
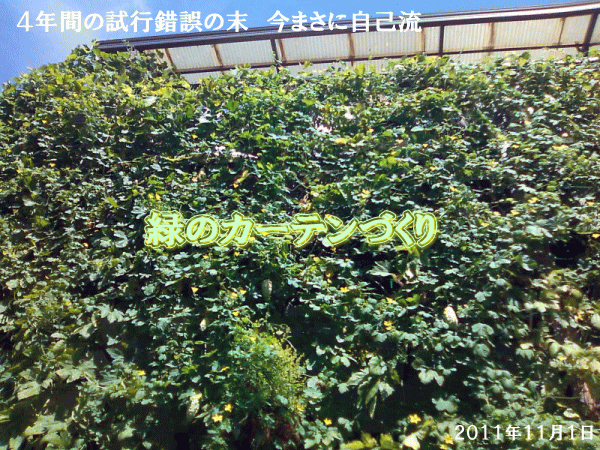 |
||
| おいしいゴーヤチャンプルでビールは旨い! しかし、プランターで育てる緑のカーテン の課題は元肥と追肥、被害の大きかったコガネムシ対策そして連作障害、更に根が真夏の日差しで大きなダメージを食らうことでした。10年間の課題解決のための戦いを写真で記録しました。目標はスーパーに並ぶゴーヤのサイズを超えることと、ご近所に省エネ効果大の緑のカーテンを知って頂くことです。 |
||||
 |
横浜市港北区の庭のない戸建て住宅でプランターによる緑のカーテンづくりに挑戦しています。 | |||
 緑のカーテン失敗から学ぶ HOW TO 2年目にバーコードにもならず失敗したという経験を生かして、プランターで緑のカーテン作りの根張り抜群の効果 |
||||
| 失敗の3連発を積み重ねて少しづつ成果の出た・・・我流緑のカーテンづくりを紹介いたします。 | ||||
| 第一回目の体験 肥料がいることの気付き 土が基本と気付きました。 |
種から芽が出てプランター用の土を買ってきてせっせと水やりをしました。バーコードにも成りませんでした。 2008年8月2日の写真が右です。 考えられる原因 栄養不足 元肥料も不足 追肥料も不足 基本的に野菜を私が理解していません。 |
 |
||
| 第二回目の体験 虫対策の気付き |
2009年8月12日葉っぱに元気がありません。 なんと土の中から出てきたのはコガネムシの幼虫でした。根っこをかじられて、太陽の高い内は、しおれていました。 腐葉土がコガネムシの幼虫に良い環境を作っていました。 |
.jpg) |
||
| 第3回目の体験 病気対策の気付き ↓ 自慢の緑のカーテン 2011年 |
2010年8月13日弦割れ病が発生。 連作障害を起こしたようです。 7月28日 正面の苦瓜の葉が熱い日差しにしおれて元気がありません、、大事を取ってすべて処分。前日1/3刈り込みましたが水を十分に汲み上げていません。 昨年のヒョウタンはつる割れ病で枯れました、その同じ位置です、土は当然プランターも取り替えました・・・・・が?。7月30日全て下記のプランターの苦瓜を処分、やはりつる割れ病と判断しました。処分後下の写真さらにコガネムシの幼虫が大発生していました。捕殺400匹を数えました。 |
|||
| 第4回目の体験 水やり失敗の気づき ↓ 2018年7月29日 |
2018年7月29日 ゴーヤの収穫も極端に少なく大きさも大きくならず葉の色も黄緑掛かって少し元気がないように思える 苗木の時期に保水対策ワイヤーネットを曲げてアルミフォイルで囲み中に水苔を入れて毎朝たっぷりの水やりが原因で根の成長に異常をきたしたのではないかと推察 しっかり根を張ったうえで水苔の対策は有効だと思える |
|||
 |
 |
 |
 |
|
| 第5回目の体験 低温でうどんこ病発生 ↓ 2019年7月21日 |
 |
 |
令和元年(2019年)7月に東京で夏日(最高気温が25度以上)にならなかった日はすでに8日もあり、12日の最高気温の予想も23度と夏日ではありません。
平成の30年間で、7月に8日以上夏日がなかったのは、平成5年(1993年)と平成15年(2003年)の2回しかありません。つまり、16年ぶりの寒い7月ということができそうです |
|
| 2019年07月21日 横浜 | データ | 時刻 | ||
| 最低気温(℃) | 24.4 | 04:46 | ||
| 最高気温(℃) | 28.5 | 15:12 | ||
| 最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.2(南東) | 11:04 | ||
 |
2016年根の張りの良かった純白ゴーヤには直射日光の輻射熱を防ぐためにアルミホイルを上段の鉢の壁面と上部の地表にも被せる(①土の表面から蒸発を防ぐ、②鉢の温度上昇を防ぐ)ように施していた結果、左記のような抜群の根張りが見られたこれを教訓に来年の上段のプランターにはすべてアルミホイル(梅雨明け)を巻きつけることにした。夏場に地熱をあげないこと沖縄でも地温は22度前後だと思われる、保水は水苔を周辺に積重ねてタップリの水やりが一番 |  |
||
 |
夏場保水対策2下段の手前にハンガータイプのイチゴプランターを水苔を敷いた上に乗せることでゴーヤの鉢の保水性を高める、昨年はこの水苔にも根が張って隣のプランターにまで伸びていた 2017年保肥力アップにも効果的だと思うので今年は肥料も入れてみることする |
|||
 |
2018年プランターによる緑のカーテン究極の保水対策発見 ワイヤーネット80×29.5㎝(百金購入)をコの字型に曲げて2段目のプランターを抱きかかえるようにセットし、中に水苔を敷き詰める、中央には土を入れてコンパニオンプランツのネギを植えた2018年は失敗に終わる 来年は根が十分に成長してからゴーヤが水分をいっぱい欲しがる時期に再度挑戦 |
 |
||
 |
||||
| 緑のカーテン運動 土づくりの大切さを学び、いろんな病気も体験し、害虫に侵され 今年こそはコガネムシの幼虫に侵略されない立派な緑のカーテンを育てたいものです。 (その後コガネムシは土に潜り込み卵を産むことを知り 成虫を土に潜らせないのが対策と判明 今はほぼ完全に対策で来ている) ニガウリ(ゴーヤ)の植え時は5月の中旬ですが、この時期には苗の販売がほとんど終了! 早め(連休前)に買って暖かいところ(室内とか)で保管又は防寒対策をして定植がお勧め、水さえ切らさなければ1週間以上は大丈夫! |
||||
| 土づくり ニガウリは連作障害を起こします。同じ土に毎年植え込むと、病気にかかりやすくなります。「弦割れ病」に昨年は侵され1本が7月に全滅しました。 1.アルカリ土壌を好むニガウリの土は、苦土石灰を大量に混ぜ込み弱アルカリの土壌を作ります。 ※鹿沼土とピートモスは強い酸性なので石灰を多めに混ぜ込む雨も酸性雨です 実を付けるために苦土(炭酸カルシウムと酸化マグネシウム)を混ぜ込見ます 2.プランターで育てる場合はプランターの大きさがニガウリの根っこの大きさになります。肥料は、しっかりと土に混ぜ込みます→2段重ねプランターを実施 3.昨年ダイコンを植えた土でレンゲを育てその土の改良と栄養素補給を考えて、腐葉土、牛フン堆肥を30%以上混ぜ込みました。 4.化成肥料とバットグアノ、ピートモスに油粕を適当に混ぜ込み約1カ月放置 5.ニガウリの根っこは30㎝以上深くもぐり込むので、持ち運びも考え(撤収の際)プランター2段重ねにしました。 6.苦しめられているコガネムシ幼虫対策、ダイアジノン粒状も混ぜ込み、あの手この手ですが失敗 7.コガネムシと言うよりコガネムシの幼虫対策は卵を成虫に産ませないことに気付き成虫を土に潜り込ませない不織布の防虫対策 |
||||
 |
||||
| 天日干しをしている土、越冬コガネムシの幼虫を1匹発見しました。収穫の後の土は天日干しをしてフルイにかけコガネムシの幼虫を取り除き元肥を施し寝かせています。 | 苦土石灰、腐葉土、牛フン堆肥、ピートモスを加えました、ダイアジノン粒状も!バットグアノが良いとのことでこれも 油粕、化成肥料と一緒に混ぜ込みました。 | スコップでしっかりと混ぜ込んでいきます。 腐葉土、完熟牛フンたい肥も30%入っています。 |
土づくりのストックです。どんどんと土があふれていきます。家の周りにとりあえず撒きましたが、もういっぱいです。1年で半分ほど処分することになりました | 今では米ぬかも微生物の繁殖に良いとのことで近所の精米者から無料で頂いて混ぜ込んでいます |
| プランター栽培のコツ ニガウリはアルカリ性の土を好みます。苦土石灰などで土を中和して、堆肥、肥料を混ぜて寝かせます。1ヶ月くらいと本に書いています。 プランターで育てる場合は連作に注意、苗は接ぎ木したものが障害を起こさないそうですが、価格が高い2倍から2.5倍の苗になります。 ドカーンと腐葉土、又は牛フン堆肥を混ぜ込んで(50%以上あってもいいかも)苦土石灰を(5%以上)多めに入れてもPHはほんのアルカリ性になるくらい 参考「苦土石灰は重さで販売 赤玉土15L 10㎏ 鹿沼土17L 7㎏ 腐葉土 20L 5㎏ 完熟牛フン堆肥 20L 7㎏ 赤玉土 7対3 腐葉土 10L 10㎏ 野菜の土(ハイブリッドと明記) 20L 10㎏」 プランター栽培は栄養分はそのプランターで最初から確保が基本だと思います(肥料は追肥が効きます)化成肥料を元肥として混ぜ込む。 『牛フン堆肥』は肥料ではありません土壌改良です 肥料は失われた栄養の補充をするので、元肥として十分に混ぜ込みます、ただし入れすぎると 植物より水の濃度が植えた植物より下がり茎から土へ水分移動する逆流により根が傷み水の吸い上げが悪くなってひどいときは枯れてしまいます。肥料焼けです※1対策 苦土石灰の量:10リットルの用土のpHを1あげるのに必要な石灰の量は、消石灰で12~20g、苦土石灰で20~25gとされています。日本は雨が多い国です。雨水は、(大気中のCO2を溶かし込んでいるため)概ねPH5.6程度の酸性を示します。また、土中では、微生物の活動によってCO2濃度は大気中よりもはるかに高く、これを溶かし込んだ土壌溶液のPHは5以下にまで下がる可能性があります。 ※1肥料焼け対策 たっぷりの散水(鉢底から流れ出てもさらに水やりを2~3日繰り返すこと |
||||
| 緑のカーテン日記 緑のカーテン学び 虫コレクション(青虫達) 野菜たちの病気 TOPページ |
||||
| 底の穴から根っこが下のプランターに伸びていく予定です。 万一の産卵にも丸々太ったコガネムシの幼虫は抜けられないと考えています。 鹿沼土は敷き詰めるときれいですが酸性ですのでゴーヤにはマイナスになる、中和が必要 |
||||
| 苦瓜(ゴーヤ)の栽培(ウリ科ツルレイシ属) サカタのタネHPより抜粋 栽培の環境 日当たり、水はけ、風通しのよい畑で栽培します。 土づくり 植えつけの約2週間前に1㎡当たり苦土石灰150g、 1週間ほど前に完熟堆肥3kgと有機配合肥料80~100gを目安に施します。 うね幅 100cm 株間 90cmを標準とします 管理のポイント 栽培期間が長いので、生育の様子を見ながら、株のまわりに追肥します。 ※ ニガウリは低温には弱いので、地温が十分に上がってから植えつけます。 防害虫 病気には強い作物ですが、うどんこ病やべと病などを予防するため、株間を広くとり、日当たりと風通しをよくします。 つる割病 ウリ科作物の連作は、つる割病が発生しやすくなるので避けます。 害虫 アブラムシは、葉に集団で寄生して吸汁し、株を弱らせます。 ハダニは葉裏に強く散水をして、流し落とします。 |
||||
武村電気製作所 土壌酸度計電池不要 我が家の土壌は弱アルカリに向いていました。 |
㈱イ―ライフ商品です。小バエがいっぱいくっついています。こんなにいるものかと感心しました。 |
プラスチックの被覆鉄線で補助金具を作ってマルチなどを抑えっています |  リピートタイで リピートタイで支柱を組む ラマンタイトン株式会社制 |
|
| レンゲのプランターが緑のカーテンの土になります。 | ||||
| 2011年3月31日 | 3月27日 | 3月25日 | 3月9日 | 4月2日 |
| レンゲのはにもハモグリバエを発見、摘み取り撤去。4月4日人参を栽培していた土、苦土石灰を混ぜ込んで天日干し奥のプランタ-レンゲです。もう少しで満開 | 鯉のぼりも風に乗って大きくふくらみ優雅に泳いでいます。ヨネヤマプランテ―ションには、キュウリの苗とナスの苗が出ていました、今苗を買って育てるのは少し危険です、温度が下がる時期があると持ちません、やはり苗は5月の連休明けがベストだそうですが、苗が売り切れる場合があるので注意です。温室のような囲いが出来れば今でも苗を植えても大丈夫のこと。ネット張りのセットは手軽ですね、今年は緑のカーテンがブームになるかも。土が大切です。 | |||
| レンゲ畑になりました。大きなプランタ-3つにめいっぱい広がったレンゲです。この土とプランタ-が緑のカーテンの主役になります。20日前後に土づくりをします。今年は省エネでさらにブームになると思います。いよいよコガネムシとの戦いが始まります。今週末にはゴーヤノ土づくりのためにレンゲは摘み取りをします。 玄関の花を夏向きに変えましたレンゲの花のプランターを全て緑のカーテンを育てるための土づくりに刈り取り土の中へ敷き込みました。出来れば連休明けに苦瓜を植えたいと思っていますが、花屋さんではすでに苗を販売しています。 今から植えると、もし寒さがぶり返したときに、苗が溶けてしまうことがあります。カバーの出来る状態ならいいんですが、我が家はご覧の通りそのままです。 |
緑のカーテンのネット用キットの販売を見つけました、パイプがスライド伸縮性です。便利手軽 | |||
| 4月20日 左ゴーヤの土づくり、寝かせている間にコガネムシが卵を産みつけないように不職布でカバーしました。コガネムシが活動するのは5月に入ってからだと思いますが、早めの対策。腐葉土、牛フン、肥料を混ぜ込み |
4 | |||
 |
||||
 |
||||
| 2011年4月20日 ニガウリの種をポットに植えました。3粒づつそして暖かいところに保管です。毎日水やり、早く芽を出せ太レイシ |
2011年5月3日 ヨネヤマプランテーションで購入した苗です。府とレイシと右が白ゴーヤ、種からのゴーヤはまだ芽が出ていません。温室(衣装ケース)へしばらくは寒さから保護です。 |
2011年5月4日 ニガウリの苗を購入、左のポット郡はオクラ、苗の周辺はニガウリの種を植えたポット、いすれのポットも茎の下に種が顔を出しています。まだ寒いので定植はしません。 |
2017年4月18日 春の嵐で左記が折れたあばしゴーヤ 摘芯には少し早いが頑張って成長してもらいたい |
バットグアノはコウモリの糞でリンが多い 花が多く咲き実が肥大する効果と甘さが増幅 この肥料は、たくさん苗にあげすぎても根っこが肥料やけしにくいメリットがあそうです。 |
| 土づくり ゴーヤはアルカリ性の土を好むので苦土石灰を混ぜ込んで土嚢に入れて1ヵ月ほど保管また ねぎとの相性も良く同じ鉢に植えてやるとコガネムシの産卵を防ぐ効果もあった、夏場は大量の水を葉から発散するため鉢の上に水苔を乗せて保水効果を高めたり1日2回の水やりを実施更には霧も散布する器具も取り付けた 水対策で費用対効果があったのはアルミホイルを地表にかぶせ鉢の周りにも巻きつけることで地表面からの蒸発を抑えることができた |
||||
 |
||||
成長の違う苗を植えると、成長の早い苗に陣取られ、遅い苗の成長が思うようにいきませんでした。 今は1鉢1苗です。 |
||||
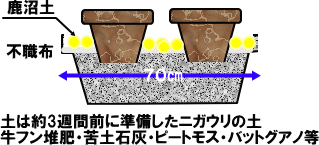 ニガウリの根っこは30㎝以上したに伸びるそうです。新戦力のぺジタブルポット、と大型プランターの2段重ね。 ニガウリの根っこは30㎝以上したに伸びるそうです。新戦力のぺジタブルポット、と大型プランターの2段重ね。コガネムシ対策 不職布で下のプランターに外からのコガネムシの産卵を阻止、丸型のプランターには、ここダメシ―ト・パーライトと鹿沼土、パーライトと不職布と鹿沼土、パーライト・ヤシの繊維と鹿沼土の3つの方法で試します。 コガネムシは土の中に潜り込んで産卵します。潜らせない対策が最善でした。・・・・無農薬 2015年も2段積みは行っていますが、下段の上に丸型の鉢1こにしています。 曜日変えて、菌の黒汁1000倍(連作障害防御) と住友液肥2号500倍に薄めて散布(栄養補給週に1回) |
||||
| 今年のコガネムシ対策はこの2段重ねのプランターです。上の丸い鉢にも不職布の上にヤシの繊維の蓋をして鹿沼土をかぶせ アルミ線で押さえています。深さも十分に確保しています。丸型の鉢は10号28.1㎝と深型10号35.1㎝の2種類です。牛フン堆肥も腐葉土もたっぷり混ぜ込みました、肥料はバットグアノも苦土石灰もピートモス、油かす化学肥料を混ぜ込み、PHは6.5近くになっています。 | ||||
| 2011年5月12日 買ってきたニガウリの苗を定植。ヨネヤマプランテーションで5月3日に購入、今日まで衣装ケースに保管していました。 |
白レイシ接ぎ木なし | 普通の太レイシ接ぎ木 | 5月19日 種から育てた苦瓜1本を定植しました。 5月20日 ニガウリの芽をカット(摘芯) |
|
 |
||||
| 5月20日南面のゴーヤのネット張り完了 ニガウリのネットはいろんなサイズがありました。我が家の主流は1800×2700が2階からは使いやすいと思っています。縦長で使うと1800×1800ネットを継ぎ足すとぴったりです。ネットを支える棒は縦使いでも横使いでもきっちりと張ることが出来ます。ネットとネットの重ね白は一マスで十分でした。台形も簡単に作れました。今年はゴーヤは、苗から定植したのは2鉢です。苗を買ってきて定植までは、コンテナに入れて暖かくなるのを待って定植しました。(苗が品切れしそうとのことで)早目の購入、種から5本!この種がやっぱり成長が遅いし弦も細い。しかも6月は異常に暑い。まだまだ試行錯誤が続きます。 |
|
|||
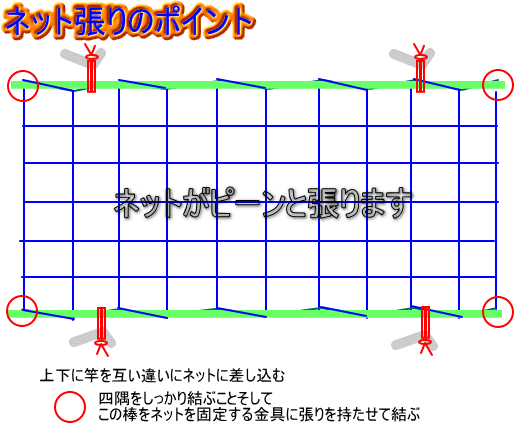 |
||||
| 水やりのホームページを発見 http://www.flower-toya.jp/info/200409.html 邪葉館 http://www13.plala.or.jp/jayokan/index.html 水やりは鉢の表面の土が乾いたらやる どんな植物だろうとも鉢の底から流れ出るまでたっぷりとやる 水やりの時間は午前中、日が昇りきる前、10時くらいまでにやる 夏は日中の高温時には絶対に水をやらない 水やり、肥料、植え変え、挿し木、観葉の基礎、古土の再生を分かりやすく説明しています。 |
||||
| 2011年緑のカーテンの準備完了です。南面のニガウリ、ヒョウタン、朝顔の定植 こんな記事が載っていました。 「3月25日から4月7日までの売上を見ると、つる性植物の種は前年比131%と大幅にアップしました。また、苗も好調で、横浜にある直営店の売り場ではゴーヤやヘチマなどが飛ぶように売れています。4月16日から1カ月間で、ゴーヤが前年比159%、ヘチマが前年比212%、ヒョウタンが前年比198%となっています」(サカタのタネ広報宣伝部・淡野一郎さん) |
||||
| 遅れた種から育てた苦瓜です。6月になって定植しました。(これが問題だったんです。) | ||||
| 5月26日 | 5月27日 | 5月29日 | 6月5日 | 6月5日 |
 |
||||
| 毎日の水やり夏場は朝夕2回水をやりました。 毎週金曜日は液肥、月曜日は菌の黒什、ときどきぼかし肥料にバットグアノ(花をたくさんつけてみも大きくなる)リン肥料です。 2017年は土再生に菌の黒汁を使い液肥は時々ジョウロで水やりの時に投入 |
||||
| 6月8日やっと成長期に突入 | 6月13日 | 6月14日 | ||
| 2011年6月19日ニガウリの葉がかじられていますが、犯人の特定できませんでした。ダイアジノン粒状をまきましたが翌日も葉の上に糞を発見、6月21日不職布をかぶせて様子見です。21日朝、ふんはみつからず!成功かも? | 6月21日 ぐんぐん伸び始めた緑のカーテン達 |
|||
| 6月23日 苦瓜の下の葉は間引きしました。風通しを良くしてニガウリの病気防止 |
左からニガウリ、ニガウリ、ひょうたん、ニガウリ、きゅうり、きゅうりと並んでいます。 | 6月25日 東面のニガウリ花はよく咲きますがほとんどがめしべです。 |
||
| 南面2011年7月1日 | 2011年7月2日測定 | やっと10㎝に育ったニガウリ | 21㎝と大きく育った葉っぱ | |
| 東面7月5日 緑のカーテンらしくなってきました。東側から順に2階の手すりに到着しています。後植えの東面と西面の朝顔は、もう少し時間が掛りそうです。ニガウリは収穫まじかです。 |
||||
| 2011年6月29日 ネットの紐に胞子が付いています。 |
||||
| 7月に入ってから真夏日が続くとプランター栽培には大変な試練がやってきます。 1.プランター内が熱さで蒸れて根が弱ってくる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アルミホイルで日差しを反射 2.プランターの土の量だけでは保水力不足になりがち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2段重ねのプランターで土の容積を確保 3.大量の水やりが肥料を流出させて肥料不足になる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・こまめに少量づつの追肥 |
||||
 |
||||
| 2011年7月5日 ニガウリの収穫が始まりました。今年は白ゴーヤもねえから育てています。 |
||||
| 7月7日右の写真は勝手に生えてきたへちまです。昨年の種が落ちていて芽が出てきたものと思います。 | 7月10日 | 7月11日 | ||
 |
||||
| アルミホイルは表面からの蒸発を抑える効果、鉢全体に巻きつけると温度上昇を抑えさらに大きな効果が! 輻射熱(75%)を防ぎ鉢の中の土の温度上昇を防いでくれて根の張りが良く育成に大きく貢献してくれました |
||||
| 7月17日 アルミホイルは効果大 プランターの上に穴をあけ、石の重りで飛ばないように設置しました。アルミホイルは乾燥防止に効果的、丸鉢に木の柵も防熱 |
||||
| もしかするとアルミフォイル(光りもの)の効果は虫を寄せ付けない効果もあったかもしれません。 輻射熱をアルミ箔の長波長放射域での反射率は、一般には0.95 から0.97 程度ですが、10μm 以上の赤外線に対しては反射率が0.99 にもなり得ます。 静岡大学 中山 顕より |
||||
2011年はまだコガネムシの被害は確認できていません。 |
葉の大きさにはかなりの差があるも南面は緑のカーテン完成です |
追肥は欠かせません 油粕&バットグアナ、液肥(化成肥料は根っこが肥料やけするのではないかと心配です。)植木鉢いっぱいに根っこを張り巡らしています。 毎週 金曜日は液肥散布 月曜日は菌の黒汁散布を続けました。 |
||
| 2011年の反省 ニガウリは種から育てた6本と接ぎ木の苗を買ってきたのが1本、白ゴーヤは接ぎ木なしの苗から1本育てました。種からの苗は温室でないので成長が著しく遅れて未だに遅れ分を取り戻せません。2本植えたプランタンの根っこ陣取り合戦で種からの苗が負けているのではないかと思います。東面の種からのニガウリは立派に育ってきましたが。南面の種からのは(2本植え)弦の成長がよくありません。実の成長も今一つです。 |
||||
| プランターを2段積み、同じ色の付いた説明覧の苗は下でプランターが繋がっています。苗から育てたニガウリは弦の太さが太いです。 左記の1本植えのニガウリも弦は2本植えより成長しています。苗からの葉茎の太さが100玉に負けていません。 プランター栽培では1つのプランターに1本の苗がケンカせずに大きく育つポイントのように思います。 |
||||
| 2011年種から育てたニガウリ | 苗から育てたニガウリ | 苗から育てたヒョウタン | 種から育てたニガウリ | |
| 種から育てたニガウリ | 種から育てたニガウリ | 苗から育てたニガウリ | 苗から育てたニガウリ | |
| 7月21日 今までに、きゅうりの収穫15本苗の数2本 雄花雌花のバランスを考えると苗は、3本以上、必要と思います。 なす24個収穫、苗は2本。満足!!! ニガウリ27個収穫、取れ過ぎでご近所にも食べてもらっています。 |
||||
| 昨年はこの時期にコガネムシの幼虫が大発生して根っこを丸かじりされたものと思われます。 ※注意 コガネムシは土の中にもぐりこみ卵を産みつけるそうです。腐葉土や根っこを主食として、植物の勢いをなくし、そして最悪枯れていきます。 |
||||
| 原因不明 葉がかじられているハダニ?コガネムシ?よくわかりません。また、葉がなんとなく縮んでいるようです。肥料不足?肥料やけ?水不足、それともやり過ぎ? 虫コレクション 野菜の病気 |
||||
| 2011年7月24日 東の角のニガウリの葉が少し縮んでいるようです。葉が黄色くなるのは栄養不足が原因の一つです栄養を下葉の古株から元気な先の新芽に送る事で発生するそうです。 2017年 ちなみに根詰まりした場合には葉先が枯れてくると言われています。ジャスミンでも葉先枯れの現象がみられたので根をほぐし切り詰めて枝葉をカットしました、今は元気な新芽が出てきています。しかし切り詰めすぎたようで今年の花芽は少なくさびしさを感じます。 |
||||
| 7月24日 下の葉から少しづつ黄色くなってきます。 |
||||
| 葉の縮れHP検索 原因 長時間、強い風が当っていると、新しい柔らかい葉は枯れます。 気温が低く、雨が多い年に多く発生するといわれております。 病気の原因はウイルス。アブラムシのせいらしいです。 対策 根本原因は、樹木の体力体質の問題であり、環境(土壌・水遣り・日照)も含めて対応を考えたいと思います。 土壌のチェックを行い問題が無ければ、残る原因は日射の当たりが悪くなったり、栄養素が不足と考え→栄養液を与え、重なり合ってる枝や、葉を少し梳くような形で剪定します。 一日中萎れてしまっているなら肥料と水ですね。 |
||||
| 7月上旬の熱い日差しにプランターのゴーヤの葉が萎れる | ||||
| 真夏の日差しに耐える緑のカーテン7月8日朝から快晴 (東面のため午前中が日差しのピークになる) | ||||
 |
 |
 |
 |
 |
| 9時35分 朝日で葉が萎れる | 10時8分 めげた東面萎れた葉がピーク | 11時3分 東面のため日差しが和らぐ | 12時1分 葉がよみがえる | 13時15分 元気を取り戻す |
 |
||||
| 実験7月24日 空いているプランターに油粕、苦土石灰、バッドグアノ、牛フン堆肥、を入れてニガウリのプランターに乗せ上からたっぷりの水を入れて追肥を試みました。 |
||||
| 5月頃のアスパラのはが黄変して枯れるかと思ったら軌跡です。横に丸い深型プランターに肥えた土を入れて、人参の種を植えたところ底から漏れた栄養ある水分でよみがえってきました。これをヒントにニガウリにもやってみました。後で反省どうせやるなら数日おいて土になじましてやればよかった。もっと元気になってほしいという思い | ||||
| 土の準備しているときから作っておいておけばいいのかも | ||||
| 7月26日よみがえれの期待を込めて! 黄変している白ゴーヤのプランターに1週間前に作った土、苦土石灰、堆肥、腐葉土、油かす、バッドグアノ、等を混ぜ込んだ土をベースにさらに苦土石灰、油かす、バッドグアノを混ぜこんで上から水をたっぷりと流し込み液肥の代わりにしました。 |
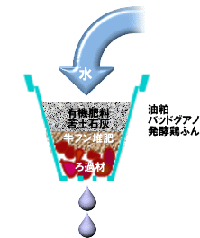 |
|||
| 来年のために! 西面の成長が期待からは大きく遅れる。 東面も少し隙間が目立つ、西面はあさがをが期待外れ勝手に発芽したへちまももう一つでした。ライナンはここへヒョウタンが良さそうです。 |
へちま |
|||
| タップの栄養がゆっくり滴り落ちていきます。効きすぎて根ぐされをおこすかも、よくわかりませんが挑戦です。プランターの栄養補給に四苦八苦です。9月まで元気な姿の緑のカーテンを維持したいものです。そういえば2日前からアブラゼミの声を聞きました。今日は夏=みんみんぜみですがその声も朝,元気な鳴き声を聞きました。夏本番です。このポットの左は鶏糞入りで少し臭います。嫌なニュースが流れています、腐葉土にも被爆したものが出回っているようです。我が家ももろにその腐葉土ではないかと思われますが、時すでに遅しです。食べちゃいました。マッ30年後にはいないかとあきらめ。 | ||||
| 今年の改善策は不職布とヤシのマットでコガネムシ対策、肥料は牛フン堆肥、鶏糞、そして2段積みのプランターに補助プランターで追肥作戦、アルミホイルによる乾燥防止、収穫は毎日で冷蔵庫がニガウリでいっぱいです。せっせとご近所に食べて頂けるようPRしています。なかなかのニガウリ営業プロになりました。 サラダには皮まで柔らかい白ゴーヤ、ニガウリは太っちょで短いのがチャンプルに美味しいです、なんて。栄養補給と土壌維持 東面の一番大きなニガウリの土壌が酸性になっていました。 栄養失調でニガウリの形がいびつになってきます。プランターの次なるハードル(難関のコガネムシ対策)は土壌維持、この小さなプランターの土壌を常を新鮮な元気のいい土壌として維持するには、何らかの知恵が必要と感じる。 ※最初の土づくりだけでシーズンを乗り越えるのは無理だと痛感、追肥も大事 |
||||
 |
||||
| 醗酵油かす液肥スーパー1 精選された有機質原料(油かす・魚粉・米ぬかなど)を 東商独自の特殊醗酵菌により特殊醗酵・液体化した アミノ酸エキス醗酵有機質肥料 |
貝殻の有機石灰を補充プランターに投入 | やっぱり破裂していました。 | 7月30日 発酵油かす液肥スーパー1を投入 (臭いけど良く効く!醗酵有機質液体肥料の決定版!と歌っています。) |
|
| 緑のカーテン90%完成 | ||||
日清ガーデンメイト 天然原料100%で環境にやさしい 「昔ながらのほんぼかし肥料」 トマト、ニガウリ、きゅうり、なす、ピーマンに追肥 |
|
|||
| ぼかし肥料の特徴 1.ぼかし肥料は生の有機物と違い、生育初期から肥料効果が期待できます 2.発酵させた過程でタンパク質をアミノ酸の形にしてしまっているので作物にとっても吸収しやすい。 3.生成過程で発生する発生物質のサイトカイニンやオーキシン、ジベレリンなどの植物ホルモンが作物の生育に非常に役立つと。 4.微生物に発酵させているわけですから、畑に投入する際に初めから有効微生物がいるので、土壌中にいる病害虫菌などのえさになりにくくなる。 百姓土日記より |
||||
 |
||||
| 8月3日 昨年を超えたと思います。ここからがコガネムシとの戦いです。昨年は7月の末に茎割れ病でメインの1本が撤去すると言うアクシデントがありました。 |
||||
| 東のニガウリも期待通り | ||||
| 8月4日 下部のヒョウタンの葉は全てカット |
8月4日 2階の手すりで行き場がなく ジャングルのようです |
|||
| 8月5日収穫 内白ゴーヤ23個1本の弦から収穫 ,太レイシ45個1本の弦から収穫 種からの小さなニガウリ16個3本の弦から収穫、種から大きなニガウリ3個1本の弦から収穫。小さなニガウリも大きなニガウリも同じ種から育てた同じ種類です。違いはプランターに1本植えか2本植えの違いで2本植えの相手方は苗からの少し成長したニガウリが競争相手になっています。根を張る競争に負けたのかもしれません。葉も小さく勢いが違います。大きなニガウリは最後の東側のニガウリです。 |
||||
| 教訓 同じプランターに植えるときは同じ成長した苗を植えるか種から育てて成長のいい苗だけを残すこと 一鉢に1本が理想かも |
||||
| 8月6日 今が元気のピークかも |
||||
| 昨年は今頃です。ニガウリに元気がなくなったのは。今年はまだ収穫があります。小さなゴーヤとナスにオクラ(昨年は葉っぱだけでオクラの収穫は0でした。立派な白ゴーヤがまだとれそうです。太レイシは、さらに太短くなってきました。弦にパワーがなくなってきたのかも(土かも) | ||||
| 2011年8月13日 | 8月13日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月22日 |
| 8月も後半になってやっと涼しくなりました。ニガウリも100本以上の収穫になり、毎日悦んで頂いてもらえる知人を探しています。大変!しかし太くて長いニガウリは少なくなりました。 | ||||
 |
||||
| 8月26日 | 8月26日 | 8月28日 | 8月28日 | |
春やさいの準備 トマトのプランターの土 フルイにかけて3つに分けました。大きな目で残った大粒は底の意思に使います。小さな目のフルイを通った土は、廃棄しました。残った土に苦土石灰、腐葉土、牛フン、鶏糞、肥料を混ぜて中しています。 |
||||
| いっぱいめしべの付けたニガウリの種を取りました。来年用です。最初、種からの成長が今一つだったんですが、1鉢に1本植えは、遜色がありませんでした。来年は2段重ねの1本植えに挑戦しようと思います。 | ||||
| 8月28日 茎も立派に育ち目いっぱいの緑のカーテンに仕上がっています |
8月28日 2階のベランダも占拠 |
|||
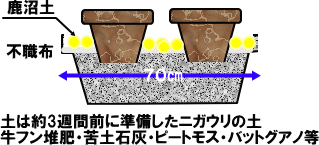 |
 |
|||
| 角型のPlanterに2段重ねをした結果上記の写真左の比較のように大きく成長の差が出ました。茎の直径にして左が3㎝オーバー右が1㎝足らずです。 右が苗から左が種から育てたニガウリです。その左が同じ種から育てました茎は2つ植えのプランターの2倍以上に成長、左の絵ように角型27Lに丸い深型10号の2段重ねです。(東面のニガウリ) 2012年の形が決まりました。 コガネムシ対策 1.5月の土づくりの時にダイアジノン粒状を混ぜ込む 2.6月梅雨明け頃にオルトラン粒状を土の上に散布して散水 これが効果的のようです。 散水はたっぷり日差しの強い日は午後にも(夕方)追肥は週1回が良さそうです。バットグアナも効果的でした。住友液肥も、菌の黒汁も連作障害防止です。 土づくりはタップリの牛フン堆肥、腐葉土、苦土石灰、油かす、化学肥料、保水効果の鹿沼土。今年はニガウリが取れ過ぎて大変!!!! |
||||
| 9月2日 初めての、ニガウリの肉詰めこれはゴーヤチャンプルの次にうまいと思いました。 |
||||
| 苗を買って植えたニガウリが右です。遅れて種から育てたニガウリを左のプランターに定植しました。針金のような茎にしか育っていません、ニガウリの実も半分以下の成長しか、しませんでした。 たぶん、右の根っこが大きく成長して養分をみんな吸い取ったと推測。 |
左の写真の種から育てた仲間ですが茎の太さも実もまったく違っていました。 結論、同時に植えるか1鉢に1本植えが最適環境をつくる |
ビールのつまみに最適、焼酎のロックでもいけます。 | ||
9月1日 |
9月7日 |
コガネムシ対策がここ4年間の大きな壁でした。 ヤシの繊維で出来たカバーを掛けての挑戦は、まずトマトで成功しました。 ニガウリも今年はまだ元気です。上の段は不職布の上にヤシの蓋、そして鹿沼土をかぶせてあります。下段は不職布に鹿沼土です。まだ結果は判りませんが、葉っぱは青々としています。コガネムシの幼虫が生息した場合は、葉っぱが黄変します。中には枯れてくるものも出てきます。葉っぱが下を向き、水やりするも元気がなくなります。H22年は7月後半に元気がなくなり、9月中旬には早々に片づけをしました。 |
||
| 9月8日 まだまだ続きそうですニガウリの収穫 大根の種付け きゅうりとへちまに雌花が咲きました。ニガウリとヒョウタンがまだ元気です。これからも少し小さくなったニガウリが収穫できそうです。 |
||||
| |
9月17日現在 まだまだ緑のカーテンを維持しています。ヒョウタンは病気にも害虫にもニガウリに比べると弱さを実感、へちまは今になって6つ目の実を付けています。肥料と水やりと鉢の深さがポイントのようです。 |
へちまを料理して食べました。味は、とにかく食べれました。ビールのつまみです | ||
| 9月17日 | ||||
| 9月19日 今年はまだまだジャングルのような苦瓜とヒョウタンのカーテンが残暑を防いでいます。 水やりは7月の中旬からは朝と夕方の2回それもたっぷり、肥料も流れて追肥も週1回以上に・・・ |
ニガウリの日干 9月17日ニガウリの天日干し 縦に2つ割、種を取って細く刻んでそのまま天日に干しました。2日でカラカラになりました。ニガウリのお茶が楽しめます。健康食でも好きになれませんでした。 |
|||
| 9月21日台風15号の当日午前7:30分頃青々と茂った緑のカーテンを維持していました。 緑のジャングル状態です。 |
ゴーヤを天日橋して織田yとして飲んでみましたが我が家にはなじめませんでした | 台風前 | ||
| 下の写真は、台風の通過した翌朝から ニガウリも、ひょうたんも、へちまも一瞬にして歳を取った浦島太郎のような現実を見てびっくりしました。強風にあおられた南面が全滅しています。植物は強風で枯れていくと言うHPを見ましたが、現実を目の当たりに見せられ 唖然とします。今年はその後涼しくなってきましたので片づけることにしました。 | ||||
 |
||||
| 9月22日 本当に浦島太郎のような南面の緑のカーテンになりました。強風が葉を枯らしていきました。 |
9月24日 東面は台風の風邪をあまり受けていません。まだしっかりした葉を蓄えています。 |
ゴーヤの肉詰です、今年の料理の新作です。なかなかの味です。 | 9月22日 台風通過 |
|
| 9月23日 | 9月24日 | 9月27日 | 2011年9月29日 | |
| 2011年9月30日緑のカーテン南面の撤収完了 台風で一挙に老いていきました。 |
6このプランター解体 右が白ゴーヤ 左がヒョウタン |
太レイシ本命になった苦瓜、立派なのがたくさん収穫できました。 | ||
 |
||||
| 白ゴーヤはなかなかの成果でした。 | ||||
| 白ゴーヤは細い根っこがびっしりと詰まっていました。苦瓜の根っこ、コガネムシの幼虫はいませんでした。 | ||||
| 2011年ひょうたんづくり | ||||
| 2011年ヒョウタンのプランターは根っこがありません見事にコガネムシの幼虫に食い荒らされていました。 | ||||
| ヒョウタンの上段のプランターコガネムシの幼虫発見 | 下段には大きなコガネムシの幼虫が30匹生息不職布の下に潜り込んでいました。ものの見事に根っこが食べられています | |||
| 太レイシヨネヤマプランテーションで購入した苗は見事に根っこを張っていました。 | ||||
| 苦瓜が一番収穫が多かった、茎です。100本以上の収穫、コガネムシの幼虫は一匹もいませんでした。茎を切ってしばらくの解体ですが根っこも一杯下段まで張っていました。 | ||||
| 全てのプランターの土をフルイにかけて大きい粒は底の石代わりに、少し小さい粒は、腐葉土、牛フン堆肥、苦土石灰、肥料、油かすと混ぜ合わせて秋の家庭菜園の土に使います。一番小さな網からすり抜けた土は処分です。なかなか乾かないのでフルイにかけるのが大変です。 | ||||
| 10月12日最後の苦瓜です、今年の緑のカーテンは終了しました。 | ||||
| 東面の苦瓜種から育てた、最後の1本です。しっかりと上下に細根を張り巡らしています。ただ上段のプランターには7㎜程のコガネムシの幼虫が10匹程度いました。8月の後半に卵を産みつけたと思います。1本の苗に1鉢で日当たりは車の影ですからあまりいいとは言えませんが、朝日をしっかりと和らげてくれました。 2012年はこのスタイルで行こうと思います。 |
||||
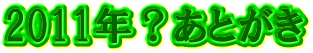 |
||||
| 苦瓜の緑のカーテンが一番作りやすいと思います。 虫に強い、病気にかかりにくい、肥料も入れ過ぎをあまり気にしなくていい、水やりで根ぐされも心配なしでし。 しかし、コガネムシの幼虫は、すごいぞ!捕獲して容器に入れると、仲間同士が咬みつき合いの死闘をはじめよりました。 こいつを排除するのが、大変。不職布で防御が今は一番の効果があり。 横浜でも、肥料をやると茎の直径が3㎝以上になりました。プランターで思い切り伸ばすと高さ5mを超えると思います。 食しても、ビールのつまみに程よい苦み、一番はゴーヤチャンプル、チップの唐揚げもいけます。今年は肉詰めに、サラダに挑戦しました。サラダは苦みと青臭さで好みに意見が分かれました。 南面と東面に緑のカーテンを育てましたが、日射については非常に効果的だったと思います。夏場の光熱費も月1万円を連続下回り家計に優しい結果になった。2日に1回は苦瓜が食卓に上りましたので食費にも、貢献! 収穫は200本を超えました。これが大変なんです、2人暮らしではさばききれません。ご近所にも、通りがかりの人にも、知り合いにも配りまっくりましたが、冷蔵庫の中は、ニガウリニ占拠されてゴーヤチャンプルの奴隷になったかのようでした。 |
||||
| 窒素肥料 | 葉をつくる 不足すると古い葉から成長の盛んな葉に移動し古い歯が黄色くなっていく 逆に施しすぎると葉色が暗緑色になる |
|||
| リン酸肥料 | 花や実をつける 根の伸長、開花、結実を促進させる 不足すると葉は暗緑色、赤褐色になり小さくなる 根の発達、花つきも悪く開花、結実も遅れる |
|||
| カリ肥料 | 茎や根を丈夫にする 不足すると葉の先端や緑が黄色くなり、中心部が暗緑色になる |
|||
| 肥料の基本HPを見つけました。参考になりました。 | ||||
| 良い土づくりは、酸素・保水・水はけ・肥料・PH・砂か粘土層か・前作(輪作)・無菌・好気バクテリア等・・・・ | ||||